- HOME
- 会社の事業の承継についての対策
- 親族への承継を想定した方法
親族への承継を想定した方法
 |
1 生前贈与の活用既に後継者が決定しており、経営者としての手腕も備わっている場合には、生前に自らの保有する株式を後継者に贈与するとともに、社長を交代する方法があります。
この方法は簡便であることが一番の長所ですが、反面、株式の評価額が高額の場合には多額の贈与税が発生するため、予め贈与税の対策が完了していることが必要です。
|
2 遺言の活用
既に後継者は決定しているものの、終身オーナーでいることを希望される方にとっては遺言を活用し、遺言によって後継者に株式を遺贈する方法があります。
この方法の長所は、死亡によって株式が分散される危険を抑止できることのほか、終身オーナーであり続けるため株主としての権利(配当等の自益権、役員選任の共益権)を保持し続けることができ、会社に一定の緊張感を与えることができることが挙げられます。
しかし、株式の価値が高額である場合には、株式を遺贈される後継者が他の相続人から民法上の遺留分減殺請求権を受け、結果的に株式が後継者以外の相続人に流出するおそれがあります。
このため、遺言を活用する場合には、予め後継者が受取人となる生命保険に加入するか、他の相続人に対して遺留分放棄手続(家庭裁判所が関与)を行わせる必要があります。
*中小企業については、遺留分に関する民法の特例を活用し、遺留分の対象から株式を除外できる場合があります(手続きには推定相続人全員の同意、経産大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要)。
3 信託の活用
信託とは、財産権を有する者(委託者)が自己または他人(受益者)の利益のために当該財産権を管理者(受託者)に管理させる制度であり、以下の特徴を有します。
1 委託者から受託者に対して対象の財産権をその名義も含めて完全に移転させる。
2 移転された財産権を、受益者のために管理・処分するという制約を受託者に課す。
以上の特徴から、委託者が将来的な相続対策という見地から信託を行う場合には、以下のメリットがあります。
1 信託の対象となる財産は、委託者の財産から切り離されて相続の対象外となるため、財産が相続によって細分化されることを防ぐことができる。
2 委託者が判断力の低下等によって信託の対象となる財産を管理することが難しくなった後も、受託者が財産を適正に管理することにより、委託者が財産の生み出す果実(賃料、配当等)を享受することができる。
3 委託者が、自らの死後に受益者となるべきものを将来に向けて順次指定することにより、いわゆる家督相続に類似した事業の承継を図ることができる。
以下、株式を信託の対象とし、委託者を法人オーナー、受託者をオーナーの親族、受益者を当初はオーナー・オーナーの死後はオーナーの子とした場合の仕組みをご説明します。
段階1
オーナー(委託者)とオーナーの親族(受託者)との間で信託契約締結
*契約は二者間で締結します。
これにより、株式の名義はオーナーからオーナーの親族に移転し、議決権の行使といった株式の管理はオーナーの親族が行います。
他方、移転した株式の配当はオーナーに帰属します。
なお、契約に格別の定めのない場合には、オーナーはオーナーの親族に対して強力な監督権限を有し、議決権行使等は実質的にオーナーの意向が反映されることとなります。
*信託契約において管理行為に不手際があるときは受託者を交代させる旨の条項を入れることも可能です。
段階2
オーナーの判断能力が低下して監督能力を失った場合には、信託監督人による監督が開始されます(予め信託契約において設定する必要あり)。
段階3
オーナーが死亡した時点で、オーナーの有していた受益権はオーナーの子が取得することとなります。
*受託者と受益者とが同一人になった場合には、1年後に信託契約は終了します。このため、受託者と受益者とがいずれもオーナーの子である場合には、オーナーの子が新たに受託者を選任して信託を継続するか否か選択することとなります。
会社の事業の承継についての対策についてはこちらもご覧ください
| ●会社の事業の承継についての対策 | ●親族への承継を想定した方法 |
| ●税務上の取扱い | ●他の相続人との関係 |
借金問題で押さえておきたい方策についてはこちらもご覧ください
| ●借金問題で押さえておきたい方策 | ●会社の再生手法 |
| ●経営者保証の関係 | ●会社の事業の承継についての対策 |
| ●親族以外への承継を想定した方法 |
| ◆当事務所の再生事例 | ◆当事務所の特徴 | ◆ご相談の流れ | ◆事務所紹介 |
通常の法律相談料は5,000円(30分)ですが、緊急性・重要性を鑑みて、企業再生・会社整理に関するご相談について初回相談料を無料(0円)とさせて頂いております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
北海道札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階 TEL:011-281-0757 (9:00~17:30 夜間・土日応相談)
初めての方でも安心してご相談いただける地元札幌市の法律事務所です。
Copyright (C) 2014 村松法律事務所 All Rights Reserved.

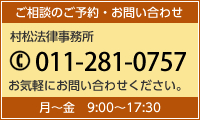
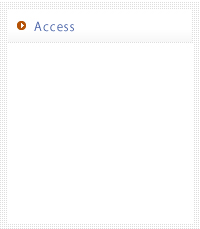
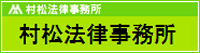
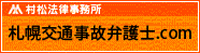
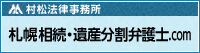
![Tactics 北海道活性化センター[タクティス]](/img/common/ImgLS6.jpg)
